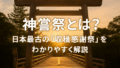10月になると、古くから日本ではこの月を「神無月(かんなづき)」と呼びます。
文字通り「神が無い月」と書きますが、実は神様がいなくなるわけではありません。
この呼び名には、神々が一斉に“出雲大社”へ集う月という、
神話に基づいた美しい意味が込められています。
この記事では、神無月の由来や意味、そして各地の神社での過ごし方を、
神職の立場からわかりやすくお伝えします。
神無月の意味とは?
「神無月(かんなづき)」という言葉には諸説ありますが、
もっともよく知られているのは次の説です👇
全国の神々が出雲大社へ集まり、
来年のご縁や運命を話し合うため、各地の神社を留守にされる。
つまり、「神様がいない月」という意味ではなく、
神々が“出張中”の月なのです。
一方で、出雲地方では神様を迎えるため、
この月を「神在月(かみありづき)」と呼びます。
同じ10月でも、地域によって呼び方が違うのはとても興味深いですね。
神々が出雲に集う理由
出雲大社の御祭神・大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)は、
「縁結びの神様」として知られています。
10月には全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲に集まり、
人々の縁(えにし)や運命、結びつきを話し合うといわれています。
この時期、出雲では「神在祭(かみありさい)」という祭典が行われ、
全国から多くの参拝者が集まります。
まさに、神々の会議が行われる特別な月なのです。
神無月の語源・ほかの説
神無月の語源には、実は他にもいくつかの説があります。
| 説 | 意味 |
|---|---|
| 「神の月」説 | 「無」は“の”を意味し、「神の月」=神をまつる月 |
| 「醸成月(かみなしづき)」説 | 新米でお酒を“醸(かも)す”月(神酒の由来) |
| 「神去月(かみさりづき)」説 | 神々が一時的に他の地へ去る月 |
どの説にも共通しているのは、
**“神と人とのつながりを思う季節”**であることです。
神無月の過ごし方
神無月は、自然が実りを迎え、空気も澄んでくる季節。
感謝と祈りを新たにするのにぴったりな月です。
この時期は、
- 神棚をきれいに整える
- 新米や旬の食材をお供えする
- 今年の感謝を神様に伝える
そんな静かなひとときを過ごしてみてください。
特に、神嘗祭(10月17日頃)を経て、
“感謝の心”を深める月としても意味のある時期です。
出雲の神在祭にちなんで
出雲大社では旧暦の10月(例年11月頃)に「神在祭」が行われます。
出雲の海に神々を迎える「神迎祭(かみむかえさい)」に始まり、
一週間ほど、神々への祈りと感謝の神事が続きます。
夜の海に灯される松明や、静かに響く太鼓の音。
そこには、古代から変わらない“神々の気配”を感じることができます。
まとめ:神様と人をつなぐ、見えない「縁」の月
神無月は、神々が出雲へ集う特別な月。
けれども、神様がまったくいなくなるわけではありません。
むしろ、私たちが「神を思う」月としての意味が込められています。
この時期、ふとしたご縁や出来事に「ありがたい」と感じたなら、
それはきっと、神々のご加護かもしれません🍂
秋の澄んだ空の下で、感謝の気持ちをもう一度思い出してみましょう。