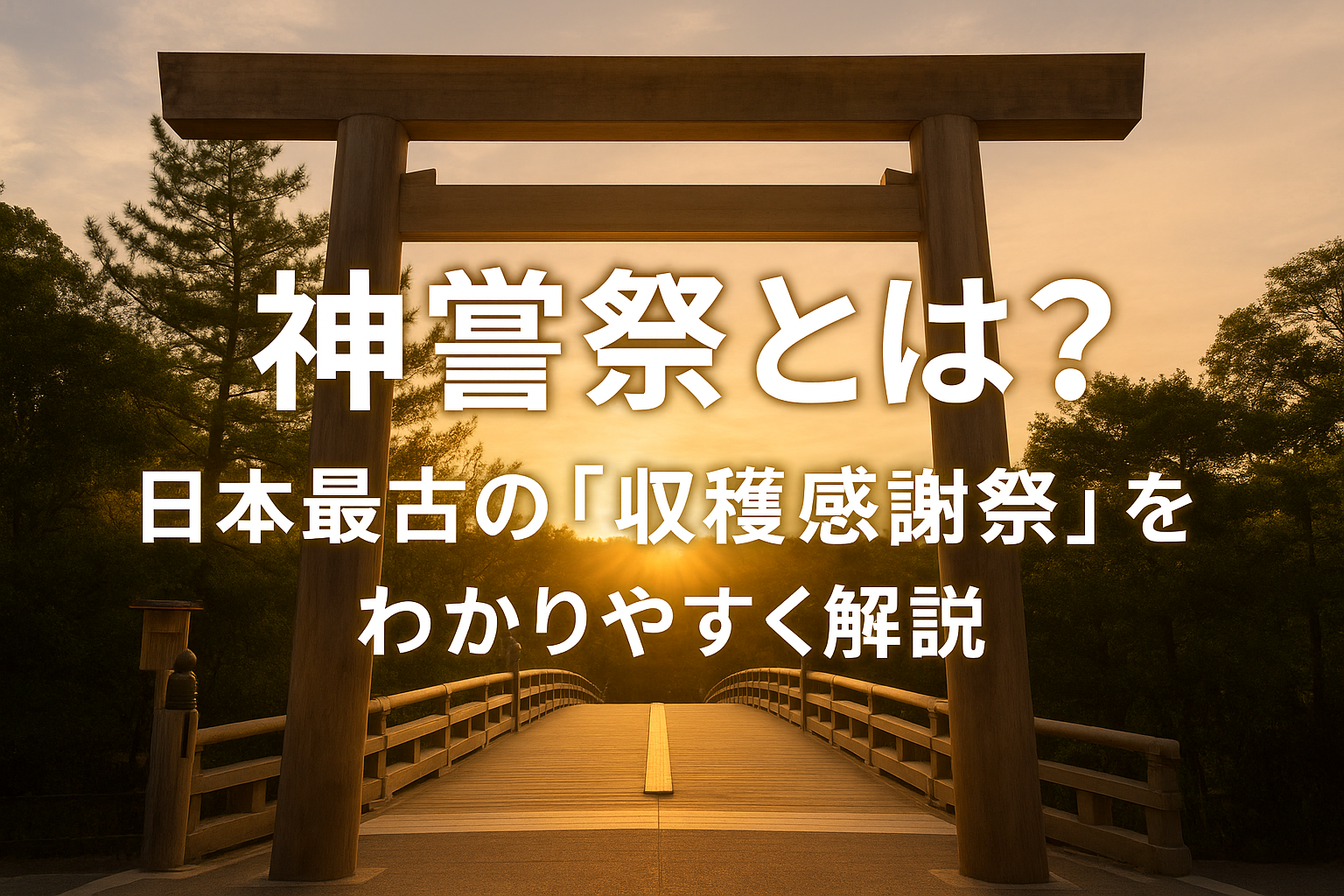description: 神嘗祭(かんなめさい)は、天照大御神に新穀を奉る秋の大祭。伊勢神宮で行われるこの神事の意味と由来を、神主の視点で分かりやすく解説します。
🪶神嘗祭(かんなめさい)という言葉を聞いたことがありますか?
毎年10月に行われるこのお祭りは、日本の「収穫感謝祭」ともいわれる、
とても大切な神事です。
この記事では、神嘗祭の由来や意味、伊勢神宮との関わりを紹介します。
神嘗祭とはどんなお祭り?
神嘗祭とは、その年に初めて収穫された新穀(しんこく)=新米を、天照大御神にお供えするお祭りです。
「嘗(なめる)」という漢字には、“初めて味わう・口にする”という意味があり、
“神に初めて捧げる”という神聖な行いを表しています。
つまり神嘗祭は、日本人が古くから行ってきた感謝の心を表す神事なのです。
いつ行われるの?
伊勢神宮では、毎年10月17日を中心に神嘗祭が行われます。
全国の神社では日付は前後しますが、
多くが10月中旬〜下旬にかけて、この神事に合わせて感謝祭や収穫祭を行います。
秋の実りに感謝し、翌年の豊作を祈る—
まさに、自然とともに生きる日本人の心を表すお祭りです。
神嘗祭の由来と意味
神嘗祭は、日本書紀や古事記にも登場する最も古い神事のひとつです。
天照大御神に新穀を奉ることが定められたのは、天孫降臨(ににぎのみことの降臨)の頃からと伝えられています。
古代から、稲作は“命の根”とされ、人々はその恵みに感謝しながら生活してきました。
神嘗祭は、自然の恵みと神への感謝を伝える最も根源的な祭りなのです。
伊勢神宮での神嘗祭
伊勢神宮では、10月15日から25日ごろまでの期間、
「外宮」「内宮」でそれぞれ厳粛に神嘗祭が執り行われます。
新米や酒、野菜などが神々にお供えされ、
神職や御師(おし)たちが神楽を奉納します。
特にこの時期の伊勢は多くの参拝者で賑わい、
全国の神社の“中心”としての荘厳な雰囲気に包まれます。
各地の神社でも行われる「新嘗祭」との違い
神嘗祭とよく似たお祭りに「新嘗祭(にいなめさい)」があります。
違いは次の通りです👇
神事名 時期 主な意味
神嘗祭 10月17日頃 その年の新穀を天照大御神に初めて奉る
新嘗祭 11月23日 収穫を全国の神々に感謝する(天皇陛下も斎行)
つまり、神嘗祭は伊勢神宮に捧げる感謝祭で、
新嘗祭は全国の神々に感謝する日という位置づけです。
まとめ:感謝の心を伝える秋の神事
神嘗祭は、古代から変わらず続く「感謝」のお祭り。
新しいお米を食べる前に、まず神様にお供えし、感謝を伝える。
その心は、現代の私たちの暮らしにも通じています。
秋の恵みをいただくとき、少しだけ神嘗祭を思い出してみませんか?🍁